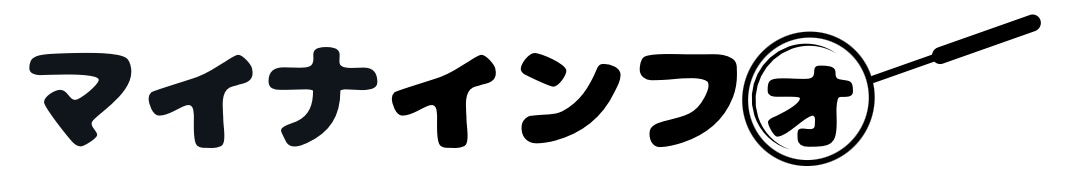海外のマイナンバー ~ドイツ編~
今回は、ドイツのマイナンバー制度について調べてみました。以下、簡単にまとめていきたいと思います。
基本情報
ドイツのマイナンバー制度に関する基本情報は以下の通りです。
| 人口 | 約8,300万人 |
| カードの取得義務 | あり(16歳以上) |
| マイナンバー(個人ID) | 納税者識別番号(11桁) 住民票番号(地方自治体ごと) |
| 利用範囲 | ・行政分野(主に税、社会保障) |
国民IDの歴史
ドイツでは、包括的なマイナンバー制度ではなく、用途に応じた複数のID番号が利用されてきました。最も重要なものは、2007年に導入された納税者識別番号(Steuer-Identifikationsnummer)です。これは、脱税対策と行政効率化のために導入され、生涯を通じて一人の個人に付与される11桁の番号です。また、住民票番号(Melderegisterauskunft)や社会保険番号も存在し、それぞれが特定の行政サービスで利用されています。
さらに、2010年からはICチップを内蔵した新しい身分証明書(neuer Personalausweis)が導入され、電子的な本人確認機能が備わりました。これにより、オンラインでの行政手続きや民間サービスの利用が進んでいます。
利活用について
ドイツの納税者識別番号は、その名の通り、主に税務申告のために使われます。所得税、固定資産税、相続税など、あらゆる税務手続きでこの番号が利用され、行政機関は個人の納税情報を一元的に管理できます。また、社会保障番号も存在し、年金、健康保険、失業手当などの社会保障サービスで活用されます。
2010年導入の新しい身分証明書には、電子的な身分証明機能が搭載されており、これを活用してオンラインでの行政手続きや銀行サービスの本人確認を行うことができます。ただし、厳格なデータ保護の考え方から、これらの番号は目的外利用が厳しく制限されており、民間企業が安易に個人の番号を収集・利用することはできません。
特徴的な仕組み
ドイツのID制度の最大の特徴は、**「目的特化型ID」**であることです。包括的な単一のマイナンバーではなく、税務には納税者識別番号、社会保障には社会保険番号といったように、用途に応じて異なる番号を使い分けています。これにより、ある特定の目的で収集された情報が、別の目的で安易に利用されることを防ぎ、プライバシー保護を重視する姿勢が反映されています。
また、この考え方は新しい電子身分証明書にも適用されており、電子的な本人確認機能を利用するかどうかは国民自身が選択できます。オンラインサービスでの利用時には、特定の目的のために最小限の情報だけを開示する設定にすることも可能であり、国民の自己決定権を尊重する仕組みとなっています。
以上、今回はドイツのマイナンバー制度についてでした。