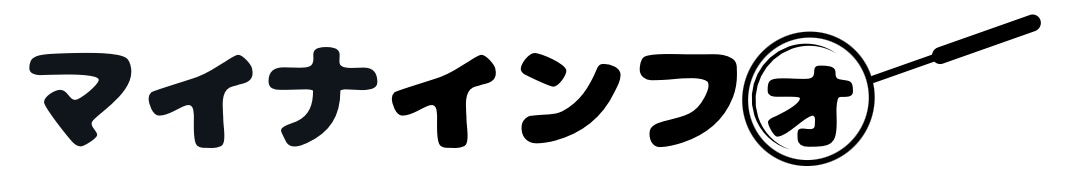海外のマイナンバー ~フランス編~
今回は、フランスのマイナンバー制度について調べてみました。以下、簡単にまとめていきたいと思います。
基本情報
フランスのマイナンバー制度に関する基本情報は以下の通りです。
| 人口 | 約6,500万人 |
| カードの取得義務 | あり(12歳以上) |
| マイナンバー(個人ID) | INSEE番号(13桁+2桁) |
| 利用範囲 | ・行政分野(主に社会保障) ・民間分野 |
国民IDの歴史
フランスでは、第二次世界大戦中の1940年代に、国民経済の動員と社会保障制度の管理のために国民識別番号(NIR: Numéro d’Inscription au Répertoire)が導入されました。この番号は、フランス国立統計経済研究所(INSEE)が管理していることから、一般に「INSEE番号」と呼ばれています。INSEE番号は、13桁の本体と2桁のチェックデジットで構成され、男女の区別、生年月日、出生地、固有番号が含まれています。
この制度は長きにわたり社会保障分野を中心に活用されてきましたが、2021年からは新たにICチップを搭載した電子身分証明書「Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe)」の交付が開始されました。これにより、物理的なカードだけでなく、デジタル上での本人確認や各種行政手続きへの利用が拡大しています。
利活用について
フランスのINSEE番号は、社会保障番号として主に社会保障制度全般で利用されています。具体的には、年金、健康保険、家族手当、失業手当などの手続きに不可欠な番号です。この番号は社会保障カード「Carte Vitale」と紐づいており、医療機関での受診や薬局での処方箋の受け取り、医療費の精算に利用されます。カードを提示するだけで医療費の払い戻し手続きが自動的に行われるため、国民はスムーズに医療サービスを受けることができます。
また、納税申告や公的機関へのオンライン手続きにも利用されており、生活に密着した多様な行政サービスを支えています。民間分野でも、銀行口座開設、保険契約、雇用契約など、本人確認が必要な多くの場面で利用されており、フランス国民のデジタルライフに深く浸透しています。新しい電子身分証明書「CNIe」と連携するスマートフォンアプリ「France Identité」を通じて、デジタル上での本人確認も可能となり、行政や民間サービスへのアクセスがさらに簡素化されました。
特徴的な仕組み
フランスのINSEE番号を用いた最大の利活用例は、医療費の払い戻しを効率化する社会保障カード「Carte Vitale」です。このカードには、本人の身元情報、保険加入状況、診療履歴などが記録されており、医療機関や薬局で提示するだけで、医療費の保険適用分が自動的に払い戻されます。これにより、国民は原則として医療機関の窓口で医療費の全額を立て替える必要がなくなり、家計の負担を軽減しています。
さらに、近年導入された電子身分証明書「CNIe」と連携する「France Identité」アプリは、デジタルIDとしての役割を担い、オンラインでの本人確認を簡素化します。このアプリを使えば、例えば行政手続きの際に書類を提出する代わりに、スマートフォンで認証を行うことができます。これは、エストニアと同様に、デジタル化を推進するフランス政府の取り組みの一環であり、EU圏内の国々とも連携した広範な利用が期待されています。
以上、今回はフランスのマイナンバー制度についてでした。